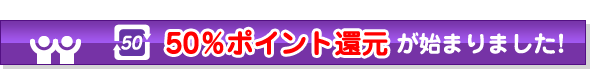
ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし ゼルダの伝説 4つの剣 ゼルダの伝説 神々のトライフォース ゼルダの伝説 風のタクト ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 ゼルダの伝説 ムジュラの仮面
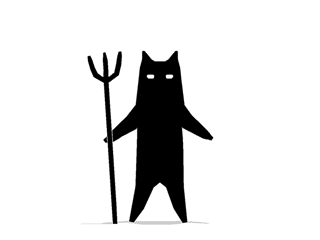 ゼルダの伝説とは
ゼルダの伝説とは |


ゼルダの伝説
ゲームタイトル検索
ゼルダの伝説シリーズ(ゼルダのでんせつシリーズ)は、任天堂が開発・発売したコンピュータゲームシリーズである。略称は「ゼルダ」または「ゼル伝」。日本国外でのタイトルは「The Legend of Zelda」で、日本版のロゴにも使われている。 、「ゼルダは、謎解き」。謎解きの要素があるゲームは第一作の発売当時は珍しく、プレイする楽しみが失われないようにという理由で、ゲーム雑誌が攻略情報を掲載する時期に規制がかけられた初めてのゲームといわれる。 特に、謎解きの難易度は、他のゲームと比べると相当レベルの高いものとなっている。この謎解きが解けずに断念するプレイヤーも少なくない。だが、反対にアクション面では、ダンジョンボスがそれほど強く設定されておらず、本シリーズがアクションをメインとするマリオシリーズと区別し、「いかに謎を解くか」を特徴的に製作されているシリーズであるということが窺い知れる。前述した通り本作の特徴として謎解きの難易度も、グラフィック同様にファンの意見、批判の対象になることが多く、最近の任天堂ソフトに多いライトユーザー思考の作品(猫目リンクに多い)は、コアユーザーからは、「簡単過ぎる」との批判が多々見られる(余談ではあるが、ゼルダユーザーにとって、謎解きの難易度は、難しければ難しいほどやりがいがあると感じる)。 シリーズはファミコン時代から続いているが、NINTENDO64以降の据え置き型ハードのゼルダシリーズは、2D型ものから3D型のものへと変わった。一方で、伝統的な2D型のものも並行的に携帯機で新作が発売されており、「ゼルダの伝説住み分け」を実現しているシリーズである。謎を解く楽しさは2D、3Dどちらも変わらない(なお、余談であるが、携帯機で発売されるものは、最近では猫目リンクの登場するシリーズのデザインコンセプトに拠るものが比較的多くなってきている)。 テレビCMなどで毎度使われることの多いお馴染みの効果音は、ゲーム内で耳にするであろう謎が解けた時のFC時代からある音である。謎を解けた快感こそがこのゼルダの伝説シリーズの醍醐味であるといえる。 ゼルダの伝説シリーズは多くの作品が漫画化されている。特に2000年に発売された『ゼルダの伝説時のオカリナ』以降の漫画は姫川明が継続的に執筆している。 『ゼルダの伝説』シリーズは、どの作品でもプレイヤーが操作する主人公の一人称から見る形で物語が進んでいく。主人公の特徴は、剣や盾、弓矢・爆弾などの多彩な武器を備えた緑色の服に身を包んだ少年(青年)というものでどの作品でも共通しており、名前や性格はプレイヤーとの一体感を持たせるために特定されていないが、1作目の主人公の名前であったリンク(Link)が『ゼルダの伝説』シリーズの主人公を指す通称となっている。 多くのシリーズ作品で重要な役割を持って登場するキャラクターに、ハイラル王家の姫君のゼルダの伝説(Zelda)と、絶対的悪の存在でありリンクの最後の敵となる魔物のガノン(Ganon)がいる。リンク、ゼルダ、ガノンの三人はそれぞれ勇気、知恵、力のトライフォースを受け継ぐ運命にあり、『ゼルダの伝説』はこの3人を巡る物語であると言える。ゼルダとガノンは、リンクとは異なり作品によって大小容姿などに差がある。特にガノンは『時のオカリナ』において人間キャラクターのガノンドロフ(Ganondorf)として登場し、近年の作品では、ガノンはガノンドロフとして登場することがゼルダの伝説スタンダードとなっている。 主要キャラクター3人以外にも、シリーズ作品には(ほぼ)同一の名前と共通した特徴を持ったキャラクターが登場している。ハイラルを統べるハイラル王、ゼルダの伝説の世話役であるインパ、リンクの愛馬のエポナ、魔物と化した子供のスタルキッド、自称妖精の生まれ変わりのおじさんチンクル、歌を愛する少女のマリンなどがそれであるが、『ゼルダの伝説』シリーズは基本的に各作品とも時系列が異なっているため同一人物ではない。ただし、例外的にガノンは各時代を渡り歩く同一人物となっている。 基本的に登場人物は人間キャラクターだが、ゴロン族、ゾーラ族のような、人間同様の文化や生活体系を持った亜人間が登場することがある。泉から現れる妖精がリンクの体力回復や手助けをする。また、ニワトリ(作品によってはゼルダの伝説コッコと呼ばれる)が登場することが多い。 雑魚敵キャラクターは各作品ともほぼ共通したものとなっており、ゼルダの伝説代表的なものにオクタロック、ライクライク、リーデッド、ギブド、モリブリン、スタルフォス、タートナックなどがいる。一方、ボスキャラクターは各作品それぞれ個性的なものが登場しているが、ドドンゴなど複数の作品に登場するものもある。 ゼルダ作品各シリーズの主人公。神に選ばれし緑衣の少年(勇者)。主に本シリーズをよく知らない人に間違われやすいが、ゼルダの伝説というのは後述のゼルダ姫の名前であり、主人公の名前はリンクである。 「勇気のトライフォース」の所持者。作品毎に出てくるゼルダの伝説勇者リンクは他の登場人物を含め、名は同じでも同一人物であるという設定ではない(外伝、続編などでは例外として同一人物が出ることがある)。なお、「リンク」という名前は、プレイヤーの任意によって変更が可能である(時に、上記のような理由から、姫の名前である「ゼルダの伝説」と間違えて付けてしまう人も多い。)、世界設定が語られる上で便宜上1作目の主人公の名前「リンク」が使われており、そのような勇者の少年の名前を象徴的に「リンク」と呼んでいるとも言える。『時のオカリナ』以降ではこの「リンク」と言う名前がパッケージや説明書にも一般的にも表記されるようになった。(主人公の名前を任意で変更可能なのは全シリーズ一緒。また、「トワイライトプリンセス」では、愛馬であるエポナの名前を変えることも出来るようになっていた)。現在では、一般的に、主人公の名前は「リンク」と言う認知で一致してきている。 ゼルダシリーズで勇者の服装が「緑の衣」とされる理由として、ゼルダシリーズの歴史上最初の物語とも言える「時のオカリナ」のゼルダの伝説リンクが、いわば「最初の勇者」であり、彼が幼少時に着ていた「コキリ族の服」が緑色だったことが挙げられる。つまり、勇者の服装はコキリ族の服装であるとも言える(これは、「時のオカリナ」での設定上の後付である)。 現在では、多くのユーザーのリンクのイメージは青年の姿となっているが、製作者側が提唱する元々のイメージにおけるリンクの姿は少年でありゼルダシリーズは「10〜12歳ほどの少年が大魔王に立ち向かい、倒すというゼルダの伝説物語」がコンセプトとされていた。実際、青年リンクが登場する作品は2008年現在、『リンクの冒険』、『時のオカリナ』、『トワイライトプリンセス』の3作品と少ない。しかもその内の『リンクの冒険』と『時のオカリナ』についてはもともと少年だったリンクがストーリーの経過を経て青年に成長したものであるため、初登場時から青年だったリンクは『トワイライトプリンセス』のみとなる。また、「時のオカリナ」に大人と子供の両方のリンクが出たのは「伝統的に子供のリンクを登場させるか」、それとも「かっこよく大人リンクだけを登場させるか」での葛藤があり結局、伝統的な「子供時代」を時代構成を分ける事で入れることになったのだと言う。そのこともあって「ムジュラの仮面」では、伝統的な「子供リンク」が完全に主役に舞い戻っている。大人リンクが圧倒的人気と認知を誇っていたにもかかわらず「時のオカリナ」以降の作品も、実は、大人リンクよりも子供リンクのほうが出演作品が多いのである。 一方で、ゼルダシリーズにおける青年リンクはシリーズの「ゼルダの伝説華」でもある。これは、特に『時のオカリナ』のリンクから始まったと思われる概念で『時のオカリナゼルダの伝説』のリンクは、いわゆる「ゼルダの伝説イケメン」であり男女とも国際的にもゼルダの伝説ユーザーに人気があった。同様に新作におけるリンクの外見は他のキャラクター以上にユーザー内で期待、意見、批判されることも多い。宮本が『トワイライトプリンセス』のインタビュー内にて「今回のリンクは、任天堂の中でも最高レベルでしょう」と語るなど青沼も「プレイヤーキャラクターなのに、キャラが立っている。妙に味がある(中略)」[2] などと絶賛され製作者側にとってもリンクの位置付けは慎重に作られている。プレイヤーの分身であるがゆえに、リンクの人物像や性格を際立って特徴付けるような「言葉」や「感情」を発しないが、そのために、感情移入して多くのユーザーがリンクという人物に想像を膨らませ、惹きつけられているのだろう。 主人公が言葉をしゃべらないと言うことが、あえてそのゼルダの伝説シリーズのプラスになっている点(任意に)では、ドラゴンクエストシリーズの主人公の設定にも近いものがある。 「大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ」に登場したリンクは本シリーズ製作者の桜井いわく「総合的解釈におけるリンクの姿」として「大人のリアルリンク」をリンクとして選択できるようになっていた(この時の最新作のリンクは、いわゆる猫目リンクだったが)。 「ゼルダの伝説リンク」とは英語で「繋げる」という意味で、「(世界に散らばったトライフォースの欠片など)全てを繋げる者」としてリンクという名前が由来と言われている。因みにドイツ語では「左」という意味がある(=Das links)。リンクが左利きなのはそのドイツ語に由来するという説や、生みの親の宮本茂が左利きであるからという説、キャラクターデザインの際に左右の装備を誤って描いてしまったものがそのまま継承されている(第1作の説明書には、右手に剣を持ったイラストが多数見受けられる)という説などがある。但し、宮本茂は「間違えて剣を左に持たせてしまった」と発言していた。 リンクの容姿は手塚治虫の漫画およびそれを原作とするアニメ『リボンの騎士』の登場人物「チンク」がモデルになっているといわれている(「リンク」と「チンク」の容姿には類似する項目が多いことから)。 衣装や色からピーターパンとの類似性を指摘されることも多い(これに関しては「中世ヨーロッパならこのような格好の少年は多いはず。関連性はない」との開発者側からの回答がファミ通に載っていた。)ゼルダ(ZELDA) ハイラル王家の姫君、主に王女。主人公の名前ではない。作品に登場する「ゼルダの伝説」は、「知恵のトライフォース」を司る。 リンクや他の例外を除いた多くの登場人物同様、各作品の「ゼルダ」は同一人物ではない。 「リンクの冒険」では、「トライフォースをめぐって起こった悶着で、初代のゼルダ姫が長い眠りについてしまったという悲劇(その際に、勇気のトライフォースも行方不明になる)を忘れないように、ハイラル王家の姫は代々「ゼルダ」を襲名している」という設定があったが、これは、全シリーズ共通の設定とも考えられる。 ちなみに作品におけるゼルダ姫とリンク(主人公)は他のRPG的な深い関係になることは極めて少なく、むしろ王家の一族である姫と勇者ではあるが一般市民という一種の格差のような設定が見える場合が多い。他社のRPG作品のような恋愛関係やその様な表現はあまりされない。一方で、リンクには他の女の子の幼馴染がいることがある。『ふしぎのぼうし』のみリンクとゼルダが幼馴染という親しい関係であった。 ゼルダは、「時のオカリナ」以降、「光の矢」との関係が深い。なお、光の矢は、「マスターソード」同様に、シリーズによく出てくるガノンドロフを唯一傷をつけることのできる武器である。「風のタクト」「トワイライトプリンセス」では、自らがその矢を射る役に回っている。 「ゼルダ」とは、生みの親である宮本いわく「ただ響き的にかっこよかったから(つまり、造語と思われる)。」ということで「ゼルダ」になったようだ。「ゼルダ」とはイディッシュ語で「幸運」といった意味を持つ。またドイツ語起源の名「グリゼルダ(Griselda)」の省略形であり、こちらは「暗い戦い(gris hild)」を意味するとされる。また名前のモチーフは、小説家スコット・フィッツジェラルド夫人、ゼルダ・フィッツジェラルドに触発され命名されたとの説もある。 『ゼルダの伝説』 (FDS・1986年2月21日)売上本数約169万本。 『リンクの冒険』 (FDS・1987年1月14日) 『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』 (SFC・1991年11月21日) 『ゼルダの伝説 夢をみる島』 (GB・1993年6月6日) 『Link: The Faces of Evil』(PhilipsCD-i・1993年10月10日) ※Animation Magic社が開発したゲーム、開発には任天堂が一切関与していない。 『Zelda: The Wand Of Gamelon』(PhilipsCD-i・1993年10月10日) ※『Link: The Faces of Evil』と同じ会社が作ったが内容は全く違う 『ゼルダの伝説1』 (FC・1994年2月19日) ※初代ゼルダのROMカセット移植版、ごく一部のみデータを変えられている 『Zelda's Adventure』(PhilipsCD-i・1994年6月5日) ※Viridis社が開発、欧州でしか売られなかった 『ゼルダの伝説 時のオカリナ』 (N64・1998年11月21日) 『ゼルダの伝説 夢をみる島DX』 (GBC・1998年12月12日)※「夢をみる島」をカラー用にリメイクした物、カラーをうまく利用した追加ダンジョンが追加されている。ポケットプリンタにも対応。 『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』 (N64・2000年4月27日) 『ゼルダの伝説 ふしぎの木の実』 (GBC専用・2001年2月27日) 『ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章』 『ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章』 『ゼルダの伝説 風のタクト』 (GC・2002年12月13日) 『ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣』 (GBA・2003年3月14日) 『ファミコンミニ05 ゼルダの伝説1』 (GBA・2004年2月14日) ※ファミコンミニシリーズの内の1作、同タイトルの移植版 『ゼルダの伝説 4つの剣+』 (GC・2004年3月18日) ※コネクティビティの集大成 『ファミコンミニ25 ディスクシステムセレクション リンクの冒険』 (GBA・2004年8月10日) ※ファミコンミニディスクシステムセレクションシリーズ内の1作、同タイトルの移植版 『ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし』 (GBA・2004年11月4日) 『ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス』(GC・Wii・2006年12月2日発売) 発表当初はGC用に開発が行われていたが、Wiiでも発売することが決定。Wii版は本体と同時発売、GC版はオンライン限定販売となった。 『ゼルダの伝説 夢幻の砂時計』(ニンテンドーDS・2007年6月23日発売) 『ゼルダの伝説』(ぜるだのでんせつ、The Legend of Zelda)は、任天堂から発売されたゲームソフトである。ただし表記はパッケージやタイトル画面では『THE HYRULE FANTASY ゼルダの伝説』となっている。日本では1986年2月21日にファミリーコンピュータ ディスクシステム用として、ディスクシステムが発売されなかった地域ではROMカセットとして発売された。 『ゼルダの伝説』 (FDS・1986年2月21日発売) 初期バージョン ハシゴが無いと取れない命の器が、竜巻に乗って取得出来る所があるなど、一部違いがある。 『ゼルダの伝説1』 (FC・1994年2月19日発売) 本作をROMカセットに移植したもの。ごく一部のみデータを変えられている。また、ディスクシステムに内蔵されていたPWM音源が使えないため、OPで印象的な笛の音などに違いがある。前述の通り、日本国外では当初からROMカセットとして販売された。 『BSゼルダの伝説』 (サテラビュー・1995年8月放送) 移植やリメイク作品ではないが、本作のシステムに独自のイベントやナレーションを追加して製作された。 『ファミコンミニ05 ゼルダの伝説1』 (GBA・2004年2月14日発売) ファミコンミニシリーズの内の1作、同タイトル(ROMカセット版)を移植したもの。ドット比の特性が違うため、若干画面の印象が異なる。 『ゼルダコレクション』 (GC・2004年3月18日交換開始) クラブニンテンドー会員特典のプレゼント。本作のほか、リンクの冒険、時のオカリナ、ムジュラの仮面を収録。必要ポイント数は500ポイントだったが、『4つの剣+』の購入者は150ポイントで交換できた。 『ゼルダの伝説』(Wii(VC)・2006年12月2日配信開始) Wiiショッピングチャンネルで500ポイントで購入できる。実はオリジナルの移植ではなく、上の『ゼルダコレクション』のバージョンであり、ディスクシステム版とは細部が異なる。また、大乱闘スマッシュブラザーズXでは名作トライアルというモードで体験版が収録されている。 ゼルダの伝説シリーズは基本的に各作品、単一の物語である。しかし、シリーズ全体には同一時間軸に置ける大きな歴史の流れが存在することが、ゲーム本編のストーリーなどから推察できる。 例えば『ゼルダの伝説』と『リンクの冒険』、『時のオカリナ』と『ムジュラの仮面』、『風のタクト』と『夢幻の砂時計』などはそれぞれの主人公が同一人物であり、比較的短い時間での繋がりが見られる。また『時のオカリナ』と『神々のトライフォース』などのように、長い時間でも繋がりが見られる場合もある。これらの点から、リンク・ゼルダといった主な登場人物は各作品に登場するが、全てが同一人物ではなく、同じ血筋の子孫か生まれ変わりと考える方が自然と言える。また宮本茂も各作品のリンクとゼルダの関連性と問われた際に、「子孫」「生まれ変わり」などの用語を用いて説明している。ただ、ガノンだけはどうやら同一人物のようで、その都度復活しているものと思われる。 このように、ゼルダの伝説シリーズには繋がりを持つことが明示されている作品が複数存在する。
