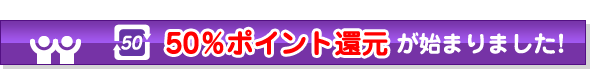
ファイナルファンタジー ファイナルファンタジーII ファイナルファンタジーIII ファイナルファンタジーIV ファイナルファンタジーV ファイナルファンタジーVI ファイナルファンタジーVII ファイナルファンタジーVIII ファイナルファンタジーIX ファイナルファンタジーX ファイナルファンタジーXI ファイナルファンタジーXII ファイナルファンタジータクティクス
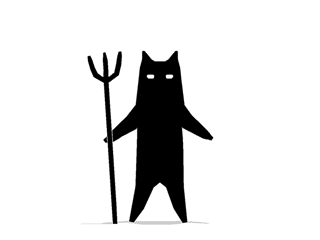 ファイナルファンタジーとは
ファイナルファンタジーとは |


ファイナルファンタジー
ゲームタイトル検索
ファイナルファンタジーシリーズ (英字はFINAL FANTASY series、略称はFFシリーズ、ファイファンシリーズ) はスクウェア(現スクウェア・エニックス)が開発するテレビゲームのシリーズ作品である。ジャンルはRPG。CGアニメ、アニメでも展開されている。 ファイナルファンタジーシリーズは1987年に発売された『ファイナルファンタジー』を第1作とする日本製のRPGシリーズであり、日本が世界に誇るゲームソフトシリーズのひとつ。シリーズ全タイトルの世界累計出荷本数7500万本(2007年11月現在)を数える。 ファイナルファンタジーシリーズの「ファイナル」は、それまでのスクウェアの業績が芳しくなく、制作者たちの間でもおそらく最後の作品になるであろうということで付けられた名称である。しかしその予想に反してヒットし、同社の看板作品となった。その後はファイナルには「究極」という意味も持たせている。 一般的に用いられる「ファイナルファンタジー」の略称は「FF」(エフエフ)であるが、スーパーファミコン時代には「ファイファン」という略語も存在した。特にファミリーコンピュータ当時は、「FF」はファイナルファンタジーシリーズだけではなく、カプコンから発売されたファイナルファイトシリーズを指すことも多く、これと区別する為に「ファイファン」と呼ばれたという背景がある。またドラゴンクエストの略称が「ドラクエ」とカタカナ4文字であり、これと差別化を図るためにスクウェアが「FF」というアルファベット2文字の略称を浸透させていったという指摘もある これまでFFシリーズでは、当時の「次世代ハード」にプラットフォームを移して初の登場となる『ファイナルファンタジーIV』(スーパーファミコン)、『ファイナルファンタジーVII』(プレイステーション)、『ファイナルファンタジーX』(プレイステーション2)が発売されると同時に、それぞれのハードが爆発的な普及をするという、言わば起爆剤のような役割を果たしていた。その後、各社がこれに追随しソフト市場全体が活性化する、という流れの繰り返しを見せている。特に1996年の「『FFVII』をプレイステーションで開発する」というスクウェアの発表は、当時3社(ソニー・コンピュータエンタテインメントのプレイステーション、セガのセガサターン、任天堂のNINTENDO64)がいずれも突破口を見出せず拮抗していたゲーム市場において、プレイステーションを当時の据え置き型ハード市場の勝利者とする大きなきっかけになった。 日本では、エニックス(現スクウェア・エニックス)発売のドラゴンクエストシリーズがファイナルファンタジーシリーズと双璧をなす存在と言われ、しばしば比較の対象となる。 先に人気を博したのは登場の早かった『ドラゴンクエスト』である。同シリーズは日本で発売された初めての大衆向けRPG作品であり、そのインパクトは大きく、遅れをとる形になったファイナルファンタジーシリーズの第1作は「ドラクエの亜種」と評価されることもあり評価が固まらなかった。しかしその後、両シリーズは「競争」しながら独自の路線を確立していくことになり、両者は「2大RPG」と呼ばれるまでに成長する[2]。 日本におけるソフト累計販売本数は、『FFVII』から『FFVIII』にかけてドラゴンクエストシリーズに匹敵するトリプルミリオンを続けて出していたが、『FFIX』以降は作品によってやや発売本数を減らしている。これに対し、ドラゴンクエストシリーズは『ドラゴンクエストVII』で400万本の大台をたたき出した後も、『DQVIII』でトリプルミリオンを軽々と超えている。ただ、これは各ソフトの発売時期におけるハードの普及率を比較すると圧倒的にFFの方が不利となっているので一概に比較できない。DQは「一番売れているハードで売る」というコンセプトに対し、FFは「FFで新しいハードの普及率を伸ばす」というコンセプトになっている。世界市場で判断した場合にはファイナルファンタジーシリーズの方が大幅に上回っていたが、『DQVIII』は日本の売り上げの多さに加えて欧米でも高い評価を得た。また日本国外でも強いFFシリーズにおいても、開発チームによって売り上げが大きく異なる(日本では売れた『FFIX』の売り上げ本数が北米では『FFX-2』よりも下であることなど)。 このような歩み寄りは見られるものの、それぞれのシリーズの独立性は失われることなく保たれている。2007年現在において、ドラゴンクエストシリーズの次回作となる『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』がニンテンドーDSで発売されることが発表された一方で、すでにファイナルファンタジーシリーズは『ファイナルファンタジーXIII』がプレイステーション3で発売されることが決定されており、両者の明確な路線の違いを見て取ることができる。 第1作『FF』から第6作『FFVI』までは、一貫して任天堂の据置ゲーム機(ファミリーコンピュータ、スーパーファミコン)向けにソフトが開発・販売された。しかし『FFVII』以降は、2008年現在発表されている次回作『FFXIII』も含めて、ソニー・コンピュータエンタテインメントのゲーム機であるプレイステーションシリーズで開発・販売されている。 『FFVII』をプレイステーションで開発したことをきっかけに、それまでハードウェアを供給し続けてきた任天堂とスクウェアは険悪な関係となった。これには、大容量のメディアを採用したハードを求めていたスクウェアの開発姿勢と、任天堂の方針が大きく食い違っていた事から離反したと、後のインタビューでは語られている(そのためスーパーファミコンの末期のスクウェアタイトルは、ソフトの発売スケジュールが全て繰り上げられた)。 これ以後、長らくスクウェアは任天堂のハードでFFシリーズを開発しなかったが、映画事業の失敗に伴い、スクウェアとエニックスの合併、社長が現代表取締役社長・和田洋一に交代、方針転換してから関係が改善し、外伝的作品『ファイナルファンタジータクティクスアドバンス』や『ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル』が任天堂のハードで発売されることになった。 『ファイナルファンタジーXII』(ファイナルファンタジートゥエルブ、FINAL FANTASY XII、略:FFXII, FF12) は、スクウェア・エニックスより日本国内で2006年3月16日に発売されたゲームソフト。 ジャンルはロールプレイングゲーム。ファイナルファンタジーシリーズの本編の12作目。プレイステーション2専用。2007年4月26日には派生作品『ファイナルファンタジーXII レヴァナント・ウイング』が発売された。またガンガンパワードに天羽銀による漫画版が連載されている。 『ファイナルファンタジーXI』(-イレブン、FINAL FANTASY XI 略称:FFXI,FF11) は、スクウェア・エニックスが開発したファイナルファンタジーシリーズ初のMMORPGである。(コンシューマーゲームとしては世界初のMMORPGとなる)。 スクウェア・エニックスのオンラインサービス「PlayOnline」を通じて提供される。また、運用開始時点で はサンマイクロシステムズ社のOS、Solarisが採用されていた。 『ファイナルファンタジーX-2』(ファイナルファンタジーテンツー、FINAL FANTASY X-2)はスクウェアより日本国内では2003年3月13日(北米では2003年11月18日、欧州では2004年2月20日)にプレイステーション2用ソフトとして発売されたロールプレイングゲーム。 『ファイナルファンタジーX』の続編(FFシリーズでは初の続編作品)である。販売本数約200万本。エニックスと合併する前のスクウェア最後の作品である。2004年2月19日に、『ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション』が合併後のスクウェア・エニックスより発売されている。こちらではボイスだけでなく主題歌も英語化されている(日本語字幕付き)。それまでのインターナショナル版とは比べ物にならないほどのイベントの追加が行われた上に、更に本作の後のストーリーであるローグ風のRPGを収録した。 基本的にXと同等程度のCGであるが、メインのリュック・パイン・ユウナではフェイシャルモーションが更に強化され、通常画面でも従来のムービーシーンに見劣らない滑らかな動きをする。 オリジナル版は株式会社スクウェアとして発売された最後のゲームソフトとなった。ちなみに、本作のULTIMANIAはデジキューブから発売されていたが、同社の破産によりULTIMANIA Ωはスクウェア・エニックスから発売された(2004年4月16日のX-2インターナショナルULTIMANIA発売に合わせ、ULTIMANIAも再販されている)。 主題歌はエイベックス所属の歌手である倖田來未が担当しており、ダンスシーンのモーションアクターも兼任した。また、インターナショナル版の主題歌はJade from sweetboxが担当している。 2005年9月8日、オリジナル版が『アルティメットヒッツ ファイナルファンタジーX-2』として低価格化されて再発売された(定価は税込み2,940円)。また、『FFX』とのセット『FFX/FFX-2 アルティメット ボックス』(税込み5,880円)も発売された。 2007年1月25日、インターナショナル版が『アルティメットヒッツ ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション』として低価格化されて再発売された(定価は税込み2,940円)。 『FFIII』や『FFV』などのジョブシステムに相当するものとして、「ドレスアップ」というシステムが採用された。従来における「ジョブ」は「ドレス」と呼ばれ、過去のファイナルファンタジーシリーズで登場したジョブをモチーフにしたドレスに加え、『FFX-2』独自のものも用意された。従来のジョブシステムと同様に、それぞれのドレスに対応した衣装の変化、コマンドやアビリティの獲得、能力値の変化などが起こる。従来との相違点としては、戦闘中にも職業を変更できることなどが挙げられる。ドレスアップを行うためには、後述の「ドレスフィア」と「リザルトプレート」が必要となる。またこのドレスアップの導入により、武器・防具の装備という概念はなくなった。ただし、特殊効果を付加する目的のアクセサリー装備は存在する。 『ファイナルファンタジーX』(-テン、FINAL FANTASY X)はスクウェア(現スクウェア・エニックス)が発売したプレイステーション2用RPG。日本国内では2001年7月19日に定価8,800円(税別)で発売。略称「FFX」「FF10」。また、「FF7」を除いてほぼ全てが欧州風の世界観を取り入れているのに対し、本作は東洋風の世界観が多く取り込まれており、異色の作品である。 2000年1月29日に開催されたイベント「スクウェア・ミレニアム」において、『ファイナルファンタジーIX』、『ファイナルファンタジーX』『ファイナルファンタジーXI』が3作同時に発表されて話題を集めた。 プレイステーション2におけるファイナルファンタジーシリーズ最初の作品である。日本国内販売本数約291万本(インター版、廉価版含む)で、プレイステーション2のソフトとしては初めてダブルミリオンを突破し、同シリーズの人気の高さを伺わせた。 北米では2001年12月18日、欧州では2002年5月24日、韓国では2002年6月4日に発売された。ワールドワイドでは約500万本を売り上げている。 同シリーズとしては初めてキャラクターボイスが採用され、よりストーリー重視の作品となり、ドラマチックな仕上がりとなった。また、7〜9のPSシリーズでも他のゲームを寄せ付けないCGだったが、プレイステーション2に移っても他を圧倒する驚異的なほど綺麗なグラフィックでユーザーを驚かせた。 なお、本作にはDVD-Video『THE OTHER SIDE OF FINAL FANTASY』が付属している。開発途中の設定資料、天野喜孝のイメージイラスト、主要スタッフや声優のインタビューなどを収録している。 2002年1月31日にアメリカ版を基にマイナーチェンジされた、『ファイナルファンタジーX インターナショナル』が発売されている。定価は7,800円(税別)、販売本数約28万本。システムやイベントが追加され、キャラクターボイスは英語になった(字幕を日本語・英語で選択可能)。アメリカ版の声優へのインタビューやCMムービー、主題歌のプロモーションビデオ、そしてエンディング後のストーリーである『永遠のナギ節』が収録されたDVD『THE OTHER SIDE OF FINAL FANTASY 2』が付属している。 ファイナルファンタジーシリーズはこれまで基本的に各作品が独立した1話完結の形態を取っていたが、本作には同シリーズで初めて物語上での続編となる作品『ファイナルファンタジーX-2』が作られ、2003年3月13日に発売された。 オリジナル版の廉価版は2003年1月16日発売の「MEGA HITS!」(定価:4,800円(税抜))と2005年9月8日発売の「アルティメットヒッツ」(定価:2,800円(税抜))の2つがあり、後者は更に『ファイナルファンタジーX-2』とのセット「アルティメットボックス」(定価:5,600円(税抜))もある。 ファイナルファンタジークリスタルクロニクルシリーズの第二弾であり、略称は「FFCCRoF」。ストーリーが楽しめるシングルプレイモードとそれとは別のマルチプレイモードがある。マルチプレイモードではDSワイヤレスプレイで協力して遊べる。但し人数分のDS本体とソフトが必要。ニンテンドーWi-Fiコネクションにも対応しており、ゲーム中でペイントしたモーグリの交換が出来る。(なお、マルチプレイをニンテンドーWi-Fiコネクション上で実現させるようなことはしていない。その理由として様々なアクションをWi-Fi上で実現させることが困難であることや、ニンテンドーWi-Fiコネクション自体の通信の遅延の問題を開発者達が挙げている[1])Wiiで発売される『ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー』(以下FFCCTCB)とは世界観・時系列での連動があるが、ゲームシステム上の連動は無い。 前作ゲームキューブ版『ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル』でシングルプレイが楽しめなかったという意見を反映し、シングルプレイモードで「FFらしいストーリー」を重視されて作られているのが今作品と『FFCCTCB』である。今作品ではその表れとしてニンテンドーDSという容量の制約のあるソフトウェアのスペックながら、一部のイベントシーンはボイス付で話が進められ、シングルプレイモードでは重厚なストーリーとがある[1]。しかしながらワイヤレスプレイができるニンテンドーDSの特徴も考えてマルチプレイモードも用意されており全く別のゲームとなっている。なお、マルチプレイモードでもフリーの冒険やクエストで対戦型のもの以外は一人でも遊ぶことが出来る。 本作品が発売する前のユーザーの間での評判は本作品と同じくニンテンドーDSで発売予定の『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』の発表初期だった頃の仕様の操作系やゲーム自体の仕組みと似ているものになるという意見や『プレイステーション』で発売された『デュープリズム』と世界観やゲームの仕組みが似てくるのではないかといった意見が多かった。なお、主人公が同じ姉と弟である双子だったFF作品として今作のエグゼクティブ・プロデューサーである河津秋敏氏が企画立案・ベースコンセプトデザインを行ったアニメーション作品である『FF:U 〜ファイナルファンタジー:アンリミテッド〜』がある。 ファイナルファンタジータクティクス A2 封穴のグリモア(Final Fantasy Tactics エーツー ふうけつのグリモア)は、スクウェア・エニックスより発売予定のニンテンドーDS用シミュレーションRPG。『ファイナルファンタジータクティクスアドバンス』(2003年)の続編で、2007年10月25日に発売された。定価5040円(税込)。 『ファイナルファンタジーXII レヴァナント・ウィング』(ニンテンドーDS)、『ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争』(プレイステーション・ポータブル)に続くイヴァリース・アライアンス第3弾。夏休みに本を読んでいた主人公・ルッソが異世界に飛ばされることから物語が始まる。『ファイナルファンタジーXII』・『FFXIIRW』のキャラクターが登場し、同作の数年後・別の地方が舞台となっている。 『ファイナルファンタジータクティクスアドバンス』(Final Fantasy Tactics Advance,FFTA)は2003年2月14日に株式会社スクウェア(現スクウェア・エニックス)より発売されたゲームボーイアドバンス用ゲームソフト。ジャンルはシミュレーションRPG。定価は6,090円(税込)で、一般的な略称はFFTA(エフエフティーエー)。ファイナルファンタジーシリーズの外伝的な作品に当たる。 ゲームボーイアドバンスで『タクティクスオウガ外伝』を制作したノウハウを持つ元クエストのメンバーが中心となって開発した。 日本国内の販売数は約44万本。海外は異例の100万本を超えるセールスとなった。 基本は『ファイナルファンタジータクティクス』と同じく、3次元空間の箱庭の中でお互い6人以内のキャラクターを駒のように動かしながら戦闘する。キャラクターを動かす順番は「味方→敵」といった一律なものではなく、アクティブタイムバトルのようにキャラクターのスピードによって順番が決められる。 『ファイナルファンタジーIX』(-ナイン、FINAL FANTASY IX、略称:FFIX)は2000年7月7日にスクウェアより発売されたロールプレイングゲーム。ファイナルファンタジーシリーズのメインシリーズ9作目に当たる。スピンアウト的な内容だが、シリーズで初めてテトラマスターFrom FINALFANTASY IXというナンバリングの続編が出た。 『ファイナルファンタジーVIII』(-エイト、FINAL FANTASY VIII、略称: FF8)は、1999年2月11日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)より発売されたRPG。ファイナルファンタジーシリーズのメインシリーズ8作目に当たる。 日本での販売数は約369万本。ファイナルファンタジーシリーズ中最高の国内販売本数であり、プレイステーションソフトとしては販売本数第2位となる(一位はドラゴンクエストVII エデンの戦士たち)。またWindows版が1999年10月3日にいくつかのバグが修正された状態で発売されている。 『ファイナルファンタジーVII』(-セブン、FINAL FANTASY VII、略称:FFVII) は、日本国内で1997年1月31日にスクウェア(現:スクウェア・エニックス)より発売されたプレイステーション用RPG。ファイナルファンタジーシリーズのメインシリーズ7作目に当たる。 本作は、シリーズ初のプレイステーション作品で、国内で約326万本、全世界で約980万本という売り上げを記録した。この記録はプレイステーションソフトで一位である。 今作以降ボックスアートはホワイトアルバムのようなシンプルなものとなった。 FFシリーズの中で最も多く兄弟作品が出されている。 現在も週刊ファミ通などのゲーム雑誌の読者人気ランキングの上位に位置し続けている。ゲームシステム面では自由度の高い、マテリアシステムが最大の特徴であるが、キャラクターごとの個性が無くなったとの指摘もある。 日本だけでなく、日本国外でも本作が発売されたが、『ファイナルファンタジーVI』までとは異なり、本作からは日本国外でも同じタイトルで発売された。このため日本国外では『FFIV』から『FFVI』までは当時欠番となり(後にプレイステーション版が発売された時は『FFIV』や『FFVI』も日本と同じタイトルとなった)、日本国外におけるFFシリーズのファンを混乱させることとなった。 1997年10月2日には、日本国内での販売本数300万本突破記念として、アメリカ版における追加部分を逆移植した『ファイナルファンタジーVII インターナショナル』が日本国内で発売された(販売本数約64万本)。2001年12月20日には廉価版『PS one Books ファイナルファンタジーVII インターナショナル』として再販された。 『ファイナルファンタジーVI』(ファイナルファンタジーシックス、FINAL FANTASY VI)はスクウェア(現スクウェア・エニックス)製作・発売の日本のRPG作品。ファイナルファンタジーシリーズの本編第6作目に当たる。略称はFF6(えふえふしっくす)。 日本国内で1994年4月2日にスーパーファミコン(以下SFC)向けのソフトとして発売された。リメイク版として、1999年3月11日にはプレイステーション版が2種類(コンビニエンスストア向けの単品と、それ以外のルート向けに『IV』及び『V』とセットにした『ファイナルファンタジーコレクション』)が発売されている。また、ゲームボーイアドバンス(GBA)版『ファイナルファンタジーVI アドバンス』が2006年11月30日に発売されており、GBA用ソフトとしては最後のリリースタイトルとなっている。 SFC用にリリースされたファイナルファンタジーシリーズとしては最後のタイトル。24メガビット(約3メガバイト)と当時としては大容量であるためか、グラフィック・音楽などの評価は高い。{要出典} また、過去のシリーズでは戦闘手段のひとつでしかなかった「魔法」の概念をストーリーの中心に持ち込んでいる。この手法は後のファイナルファンタジーシリーズにも引き継がれている。 『ファイナルファンタジーV』(ファイナルファンタジーファイブ、FINAL FANTASY V、略称FFV)は、スクウェア(現スクウェア・エニックス)発売のコンピューターゲームソフトで、ファイナルファンタジーシリーズの本編第5作目にあたる。 1992年12月6日に、スーパーファミコン(SFC)用のソフトとして発売、1998年にはコンビニエンスストア流通向けのプレイステーション(PS)版が発売され、1999年には、『ファイナルファンタジーIV』と『ファイナルファンタジーVI』をセットにした『ファイナルファンタジーコレクション』として一般流通で販売された。また、ゲームボーイアドバンス(GBA)版『ファイナルファンタジーV アドバンス』が2006年10月12日に発売されている。SFC版はシリーズ初のダブルミリオンを記録した。 『ファイナルファンタジーIV』(-フォー、FINAL FANTASY IV、略称FFIV)は、スクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売された、日本の家庭用ゲーム機用ゲームソフト。ジャンルはRPG。ファイナルファンタジーシリーズ本編第4作目。 オリジナル版は、スーパーファミコン向けソフトとして1991年7月19日に発売された。同シリーズにおいて対応ゲーム機種をスーパーファミコンに移した最初の作品である。また同年10月29日には『イージータイプ』と呼ばれる初心者向けの別バージョンも発売されている。1997年3月21日、及び1999年3月11日にはプレイステーション版が発売されている(1997年に発売されたのはコンビニエンスストア向けの単品、1999年に発売されたのは『V』及び『VI』を含めた一般ルート向けの『ファイナルファンタジーコレクション』)。また、2002年3月28日には「スクウェア マスターピース」シリーズの1つとしてワンダースワンカラー版が、2005年12月15日にはゲームボーイアドバンス版が発売されている。そして、2007年12月20日には3DでフルリメイクがなされたニンテンドーDS版が発売された。 もともと、この作品は『ファイナルファンタジーV』として開発されていたものの、当初ファミコン用として開発していた『ファイナルファンタジーIV』をお蔵入りとし、1作繰り上げる形でのリリースとなった。 シリーズ前3作のシナリオを手がけた寺田憲史によると、お蔵入りしたのは経営側が開発に介入した事が原因であり、寺田はゲームの内容にまで口を挟まれた為、ファイナルファンタジー新作(SFCの『ファイナルファンタジーIV』)のシナリオから降りた[要出典]。また最近では「FF竜騎士団」で坂口が語っていたファミコン版FFIV以外にも、もう一本田中弘道主導によるシームレスバトルの『ファイナルファンタジーIV』が企画されていた事が明らかになった。その企画はコンペに敗れ、鳥山明とコラボレーションしたオリジナルタイトル『クロノトリガー(企画段階であり、堀井雄二も参加した製品版とは完全に別物)』として企画され直すのだが、スーパーファミコン用CD-ROMの開発を任天堂が中止した為、更に『聖剣伝説2』として企画修正し発売に至った。 対応ゲーム機種がファミコンからスーパーファミコンになった事により、ファミコン時代に比べ演出効果が向上した。また、戦闘シーンは前作までのターン制ではなく、リアルタイムで時間が経過する「アクティブタイムバトルシステム(ATB)」が採用されている。このシステムは本作が初登場で、後のシリーズや『クロノ・トリガー』にも引き継がれている。また、戦闘のみ「二人プレイ」が可能になった。 本作は、タイトルロゴに現在のスタイルが採用された最初の作品である。本作のタイトルロゴに描かれているキャラクターはカインである。(DS版ではゴルベーザになっている。) 『ファイナルファンタジーIII』(ファイナルファンタジースリー、FINAL FANTASY III、略称FFIII、ファイファンIII)は、スクウェア(現スクウェア・エニックス)より発売されたファミリーコンピュータ用ゲームソフト。ゲームのジャンルはRPGで、ファイナルファンタジーシリーズの3作目。 1990年4月27日、ファミリーコンピュータ(以下FCと表記)用ロムカセットとして発売され、約140万本に及ぶ販売本数を上げ、ファイナルファンタジーシリーズ初のミリオンセラー作品となり、シリーズの人気を確固たるものとした。 2006年8月24日には、ニンテンドーDSでリメイクされた。リメイク版の詳細およびその経緯についてはDS版の記事を参照されたい。 本作は、辺境の村に住む4人の少年が、とある出来事を契機に、神秘的な力を有するクリスタルから力を授かり、光の戦士として、暗黒に包まれようとしている世界を救うために冒険の旅にでるというものである。シリーズものであるが、ストーリーは前2作とは全く関連性はない。ただ、世界観は『ファイナルファンタジー』(以下FFIと表記)に通底しており、クリスタルと世界が密接した関係を作っている。 ストーリーの途中で人の「死」に直面する場面がいくつかある。前作『ファイナルファンタジーII』(以下FFIIと表記)から仲間の死が多く描かれるようになるが、その理由として、開発中に製作総指揮・ディレクターを務める坂口博信の家が火災に遭い、母親が亡くなる事故が起きたことが挙げられている。「人の死を悲しむだけで終わるのではなく、それを乗り越える強さを持つことが大事」ということを学び、メッセージとしてユーザーに伝えるためと坂口は後日語っている[要出典]。 本作は『FFI』、『FFII』とシナリオを手がけていた寺田憲史が担当した最後の作品である。彼は本作を題材にした漫画の原作も務めている。 『FFI』、『FFII』は実験的な部分が多く、操作性などでも問題点が多かったが、本作ではそれらが解決され完成度が高かったと評価されている。また、前作までと比べてテンポよくサクサク進むこと[1]、世界設定の独自性、遊びこめるジョブチェンジシステム、ステータス異常を駆使しての攻略など、「『FF』シリーズ中最高に遊びこめる作品だったとの評価も多い」と言われている[2]。 タイトルロゴは前作同様に鳥(チョコボ)をイメージした字体で「FINAL FANTASY」と書かれており、その背後にクリスタルのように輝く文字でIIIと入っている。またパッケージには「光の戦士」が描かれている。 当時のCMでは「最後の壮大なドラマ」とナレーションされていた。 『ファイナルファンタジーII』(-ツー、FINAL FANTASY II) は、1988年12月17日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売されたファミリーコンピュータ用ゲームソフト。販売本数約76万本。ファイナルファンタジーシリーズの第2作で、ジャンルはRPGに分類される。
